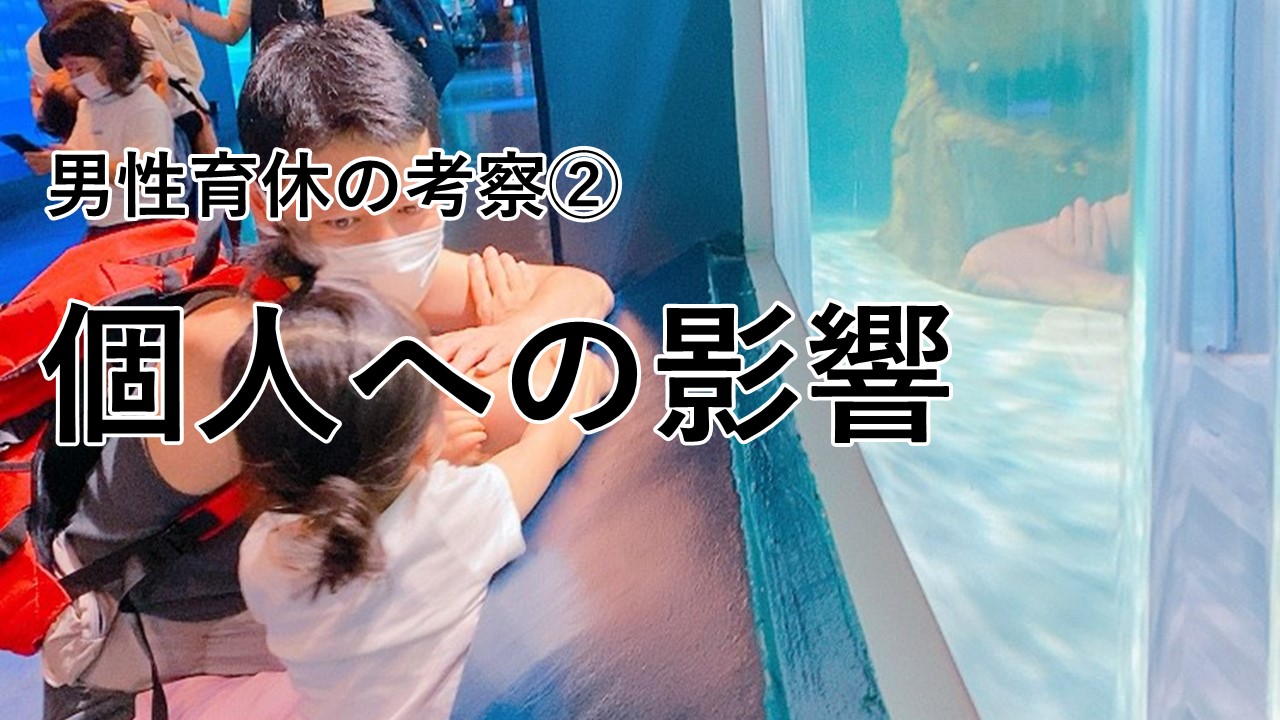
2022.08.01
男性が育休を取ると個人ベースでどんな良い影響があるのか?
当たり前ですが、育児に関して2人で取り組むので、負担が分散されるのが最も大きな良い影響ですよね。
特に、出産直後のホルモンバランスの崩れがちな時期に2人で取り組む価値は大きいのかなと思います
産後クライシス、ガルガル期、産後鬱、などこの時期はトラブルが多いので2人で乗り越えたいですね。
東レ経営研究所の調査結果によれば、出産直後を分岐点として、夫婦のパートナーの愛情が増えるグループと下降するグループに大きく2極化するようです。
これ、なんか感覚的にもわかりますよね(笑)
2人の方が育児は効率的&孤独感を回避できる
色々初めての体験の中、例えば子供が泣いている時に「なんで泣いてるんだろう?」と、仮説を立てアプローチしていきます。
ミルク、おむつ、眠い、ただ単に抱っこ・・・
こういう仕草をしている時はこういう合図なんだ、など、常にPDCAを回していく中。
これは、1人でやるよりも2人でやった方がアプローチアイディアが違うので、2倍の知見が貯まります。
なので、育児は2人でやった方が圧倒的に効率的だと思います。
また、突発的なトラブルに対しても2倍のスピードで情報収集するので、速いですよね。
そして、2人で会話するからこそ、初めての事象を1人で抱え込まずに済むというメリットもあると思います
一番のメリットは男性も育児の当事者になれること
男性育休は色々メリットありますが、一番は「男性も育児の当事者になれる」ということだと思います。
もし、生後半年間。平日は仕事、育児は土日だけだったら、と、想像してみると。
土日頑張ろうにも、妻からある程度教えてもらわないと動けないと思います。
そうすると、指示をもらえないと動けない状況になり、主体性が持てません。
母親からしても「なんで気付いて動けないの?」となると思います。
そういう意味で、男性が育休を取ることで、当事者として育児をすることができるのが最大のメリットなのかなと思います。
さいごに…
男性が育児の当事者になることが大切で、男性育休はそれができる、とお伝えしました。
ただ、一方で、高い当事者意識を持って育児をする、って、親として当たり前のことですよね。
「パパ意識高い」と、お褒めのお言葉をもらう機会が多いのですが、有難い中、やっぱり少し違和感があります。
だとしたら、世の中のママさんはもっと褒められないとおかしいですし…
でも、これが日本社会の現状なのだと思います。
当事者意識を持って父親として育児をしていても、特に褒められない社会に日本がなりますように。。。
weekly ranking
この記事を書いたブロガー
ブロガー一覧-
浅田伊佐夫さん 計16ヶ月育休取得した広告マンパパ
-

-
4歳(女)2歳(男)。40歳、広告代理店勤務のサラリーマンです。2020年4月長女誕生時に6ヶ月、2022年8月長男誕生時に10ヶ月、合計16ヶ月の育休を取得し、育児の素晴らしさと大変さを体感。「男性が当事者として育児をするのが当たり前の社会」を目指して、父目線の育児ブログを発信中。